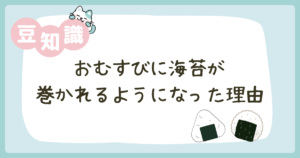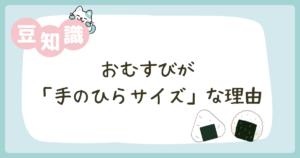俵型おむすびのルーツとは?
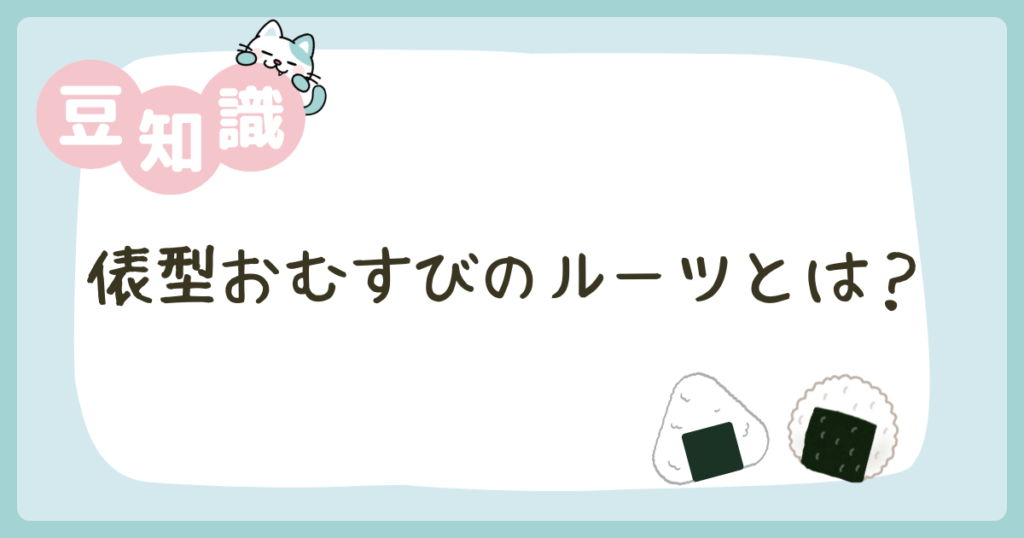
こんにちは!にゃおむすびです🐾
三角、丸、そして…俵型。おむすびにはいろんな形がありますが、今日はちょっと珍しい「俵型(たわらがた)」のおむすびについてご紹介します。
俵型おむすびは、その名の通り「米俵」のような形。ころんとした円柱型で、手に持ちやすく、食べやすいのが特徴です。実はこの形、農村部やお祭りなどで好んで作られていたといわれています。
かつて米俵は「富の象徴」。収穫したお米をぎっしり詰めて保管する俵は、農家にとって豊かさのしるしでした。その形に似せて作られた俵型おむすびには、「五穀豊穣」や「家内安全」など、願いが込められていたんですね。
また、俵型は表面積が少ないため、ごはんが乾きにくく、保存性が高いというメリットもあります。お弁当や差し入れとして持ち運ぶのにも向いており、実用性と縁起の良さを兼ね備えた形だったのです。
具を入れるにも実は適していて、中心に細長く梅や昆布を入れることで、どこからかじっても具に当たるよう工夫されていたとか。現代ではあまり見かけないかもしれませんが、実は理にかなった“実力派”のおむすびなんです。
にゃおむすびでも、時おり登場する俵型むすび。見た目のかわいらしさもさることながら、古きよき日本の心を感じられる、ちょっと特別な一品です🐾