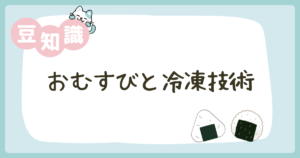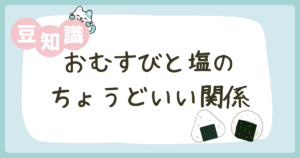おむすびと“冷めてもおいしいごはん”の関係
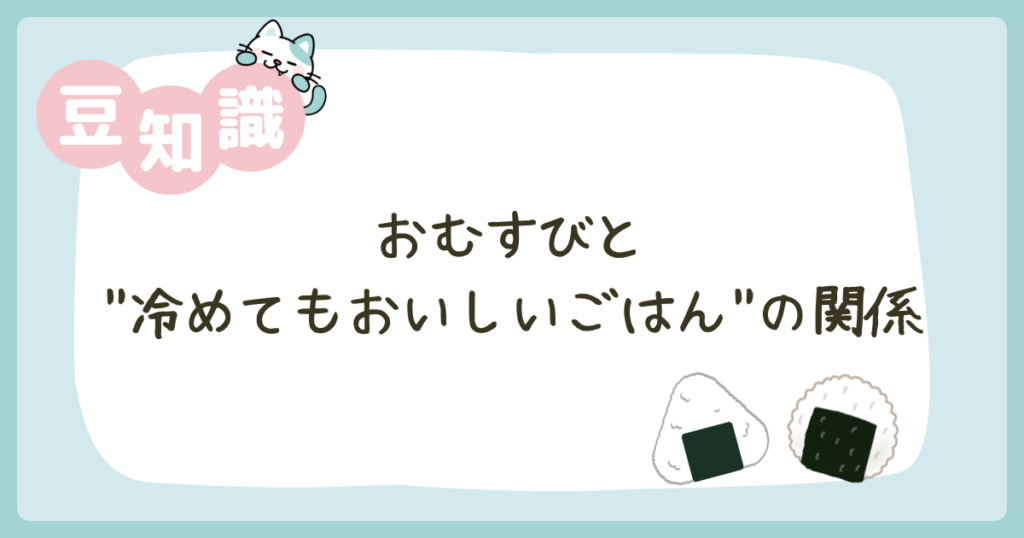
こんにちは!にゃおむすびです🐾
みなさん、おむすびを食べるとき、できたてホカホカももちろんおいしいですが、「冷めてもおいしい」と感じることってありませんか?実はこれ、偶然ではなく、ちゃんとした理由があるんです。今回は、「おむすびと冷めてもおいしいごはん」の関係について、ちょっとした豆知識をご紹介します。
おむすびに使われるごはんは、基本的に「冷めても味が落ちにくいお米」が選ばれています。たとえば、にゃおむすびでは国産コシヒカリを使用していますが、コシヒカリは粘り気があって甘みが強く、冷めてもその風味がしっかり残るのが特徴。実は、お米の品種や炊き方によって、冷めたときの味に大きな差が出るんです。
なぜ冷めると味が変わるのかというと、ごはんは冷める過程で「でんぷん」が変化します。炊きたてのごはんには、アミロースとアミロペクチンという2種類のでんぷんが含まれていますが、時間がたって冷えると、そのうちのアミロースが再結晶化し、ごはんが硬くなっていきます。これが「ごはんがパサパサする」「かたくなる」と感じる原因です。
でも、コシヒカリなどの一部の品種はアミロペクチンが多く含まれており、このでんぷんは冷めても再結晶化しにくく、モチモチ感が長持ちするのです。だから、おむすびにぴったりというわけなんですね。
さらに、炊き方も大切なポイントです。水加減が多すぎるとベチャッとしてしまい、逆に少なすぎると冷めたときにパサつきやすくなります。おむすびを作るには「やや固め」に炊くのが基本。そうすることで、冷めたときの口当たりや香りがぐっと良くなるんです。
また、おむすびにするときにギュッと握りすぎると空気が抜けてしまい、ごはん粒が潰れてかたくなってしまいます。適度にふわっと握ることで、ごはん粒の間に空気が入り、冷めてもほどよい食感が残るのです。
つまり、「冷めてもおいしいおむすび」を作るためには、お米の品種・炊き方・握り方まで、すべてにこだわりが必要ということ。コンビニおにぎりや手づくりおむすびが冷めてもおいしい理由には、こんな科学的な背景があったんですね。
お弁当にもぴったりで、時間がたっても楽しめるおむすび。お米の力を最大限に活かした日本の知恵が詰まっていると感じませんか?
次回もまた、おむすびにまつわるおもしろい豆知識をお届けします。どうぞお楽しみに🐾