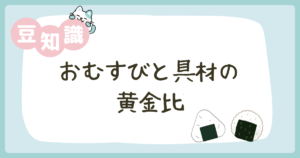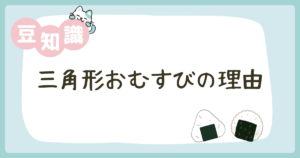おむすびと「結ぶ」の言葉の由来
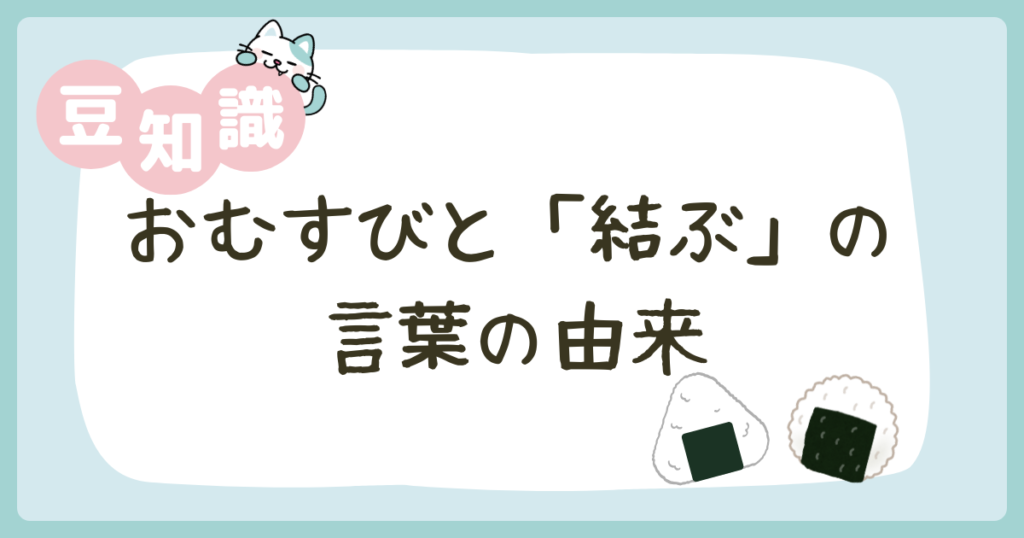
こんにちは!にゃおむすびです🐾
「おむすび」という名前、普段何気なく使っていますが、その由来をご存じでしょうか?実は「むすぶ」という言葉が深く関係しています。
古代日本では、稲には「むすひ」と呼ばれる神様の力が宿ると考えられていました。「むすひ」とは生命を生み出す神秘的な力のこと。ご飯を「むすぶ」ことで、その神様の力を形にし、食べる人に授ける意味があったとされています。つまりおむすびは、ただの携帯食ではなく「神様の力をいただく食べ物」だったのです。
また「結ぶ」という言葉には「人と人をつなぐ」という意味もあります。おむすびは昔から行事やお祭り、祝いの場に登場しました。家族が集まるとき、地域の人々が集まるとき、そこに必ずあったのが「おむすび」。形としてだけでなく、人と人の心を結びつける役割を担っていたのです。
現代でもその名残はありますよね。遠足や運動会、お弁当の定番はやっぱりおむすび。みんなで食べるとき、自然と笑顔になれるのは「結び」の力が今も生きているからかもしれません。
にゃおむすびも「食を通じて人と人を結ぶ存在でありたい」という思いを込めて日々おむすびを握っています。ぜひ、皆さんの大切な時間に寄り添うひとつとして召し上がっていただけたら嬉しいです。