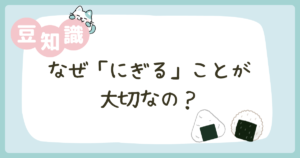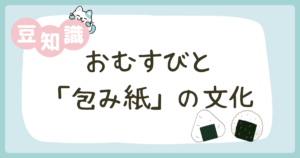おむすびと「旅」の歴史
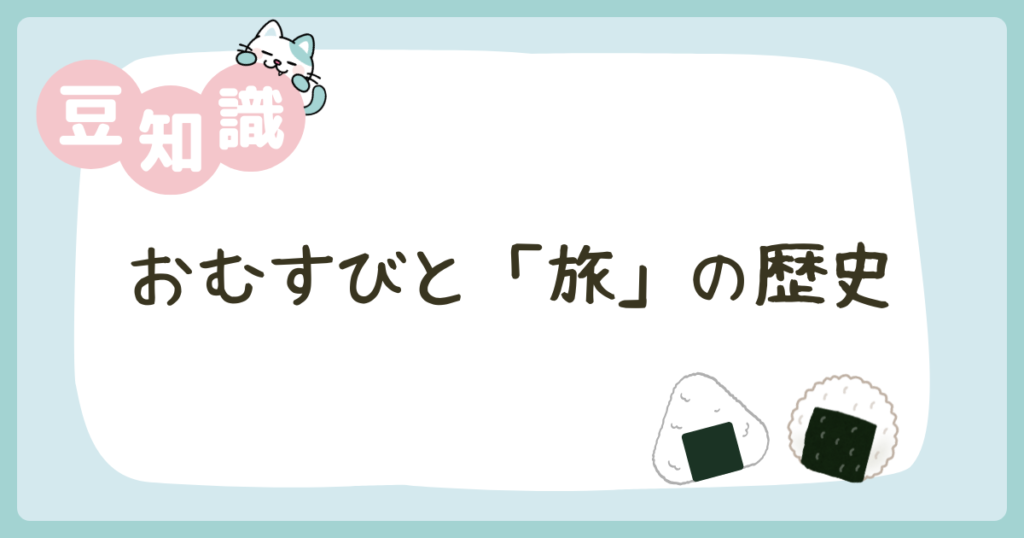
こんにちは!にゃおむすびです🐾
「旅のおともにおむすび」。そんなイメージをお持ちの方、多いのではないでしょうか?新幹線の駅弁、行楽のお弁当、遠足の定番――昔から、おむすびは“旅の相棒”として愛されてきました。でも、なぜ旅とおむすびは、こんなに深く結びついているのでしょうか?
その答えは、遥か昔にさかのぼります。
記録によれば、日本最古のおむすびの痕跡は、弥生時代の遺跡から発見された「炭化した握り飯」。つまり、古代人も移動の際に、手軽に食べられるようごはんを握って携帯していたと考えられています。
時代が下って戦国時代、武士たちは戦の合間に「握り飯」を携帯食として持参しました。いくさ場では炊事が難しいため、前もって握っておいたごはんはまさに命綱。おむすびは、兵糧としての役割を担っていたのです。
さらに江戸時代、街道が整備され、人々が旅に出るようになると、携帯に便利で腐りにくいおむすびは「旅のお弁当」として定着。紙や竹の皮に包んで持ち歩けることや、冷めてもおいしいという特性が、まさに旅人にぴったりだったのです。
現代でも、新幹線の車内で駅弁として食べるおむすびや、登山やハイキングに持っていくおにぎりなど、「移動しながら食べる」文化の中におむすびは生きています。
おむすびは、ただの食事ではなく、「安心」を包んで持ち歩くような存在。遠くにいても、握ってくれた人の気持ちを感じられるのが、おむすびの最大の魅力かもしれません。
旅の思い出に、いつも寄り添ってくれた小さな三角――それが、おむすびなのです🐾