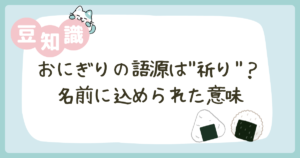なぜ三角形が主流?食べやすさだけじゃない理由
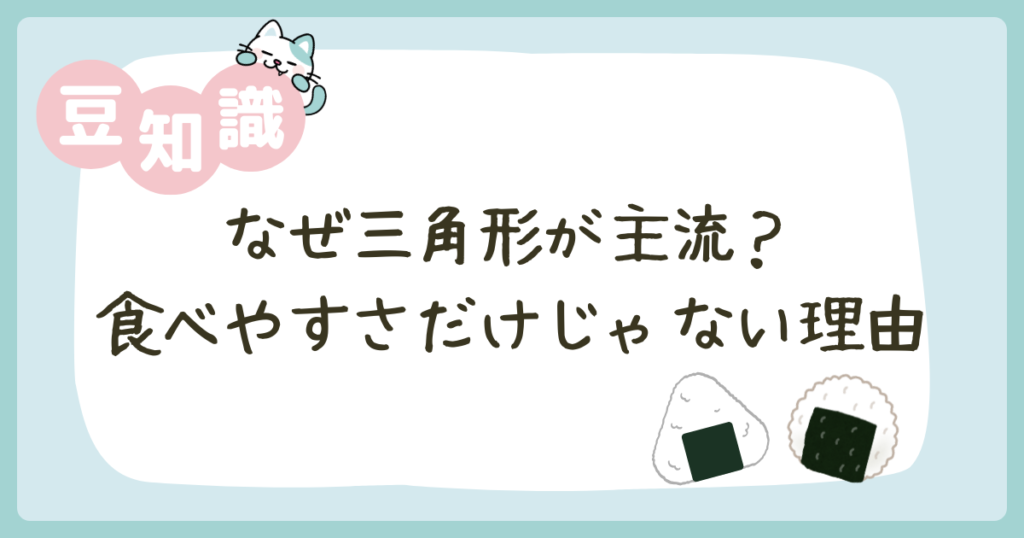
こんにちは、にゃおむすびです!
おにぎりの代表的な形といえば「三角形」。でも、なぜわざわざ三角なの?丸でも俵でもいいのに…と感じたことはありませんか?実は、三角おにぎりには“食べやすさ”以上の深い理由があるんです。
まず、三角形は「手で持ちやすい」「口に運びやすい」「崩れにくい」と、三拍子そろった形なんです。手の平で自然に作れるこの形は、頂点からかじっていくと具が中心から均等に広がる構造にもなっていて、最後までバランスよく味を楽しめるのも魅力です。お弁当箱に詰めやすいのもポイントですね。角がある分、隙間が埋まりやすく、形が崩れにくいので、昔のお弁当文化にもぴったりだったんですよ。
また、昔の日本人にとって「山」は神聖な存在でした。山は田畑を潤す雨をもたらす、大切な自然の恵みの象徴。そんな山の形を模して作られたのが、三角おにぎりだといわれています。神様への感謝を込めて山の形を作り、それをお供えする風習もありました。つまり三角おにぎりは、自然への感謝と祈りが詰まった、いわば“お供えの形”だったのです。
さらに面白いのは、地域によって「定番の形」が異なること。関西では俵型、東北や関東では三角型が主流といわれています。俵型はお米が取れる農家にとって、収穫した米俵を連想させる縁起の良い形だったんだとか。一方、丸いおにぎりは、家庭で手軽に作れる形として、子どものおやつや行楽のお供によく作られてきました。丸い形には「家庭円満」や「縁をつなぐ」という意味もあるそうですよ。
現代ではコンビニおにぎりの普及で、三角形のイメージがさらに定着しました。機械で成形しやすく、フィルム包装とも相性が良いことが理由です。とはいえ、丸でも俵でも、それぞれの形にはちゃんと意味やストーリーがあり、どれも日本人の暮らしに根付いているんです。
あなたはどの形がお好みですか?ぜひ教えてくださいね!