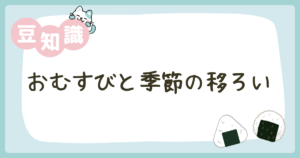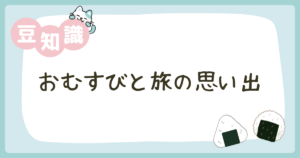おむすびと日本の道具
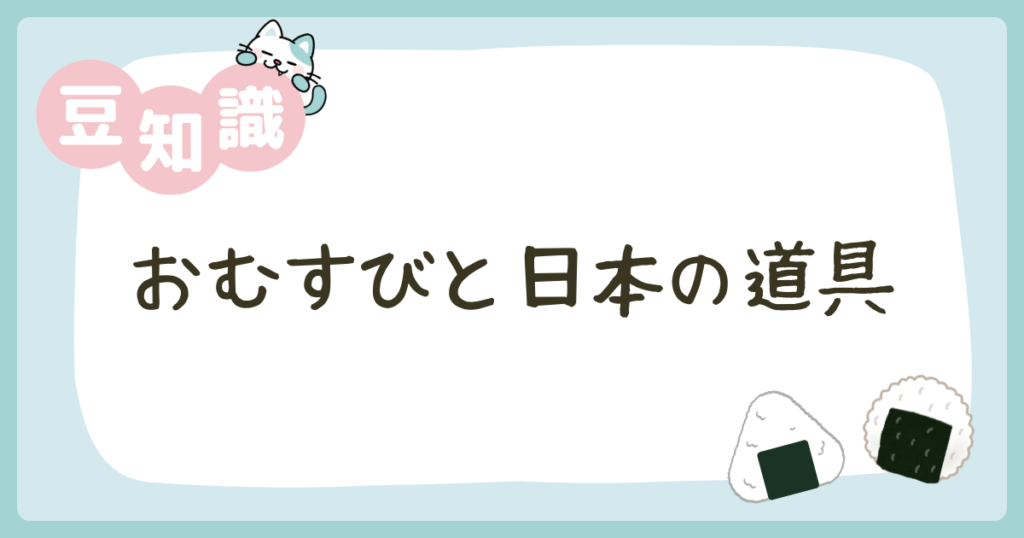
こんにちは、にゃおむすびです🐾
おむすびを作るときに欠かせないのが、「道具」です。手で握るのが基本ですが、昔は竹の皮や経木(きょうぎ)、わらなど、自然の素材を使って包むのが一般的でした。竹の皮には抗菌作用があり、ご飯を清潔に保ちつつ長持ちさせる知恵が詰まっています。しかも、ほんのりと竹の香りがご飯に移り、自然のぬくもりを感じられます。経木もまた優れもので、通気性がよく、湿気を逃がしてくれるため、時間が経ってもべたつかず、美味しさを保ってくれるのです。包みを開いたときにふわっと漂う木の香りには、どこか懐かしい安心感があります。
現代ではラップやアルミホイルが主流になり、持ち運びも手軽になりました。けれども、昔ながらの素材を使うと、おむすびの味わいが不思議と優しくなるように感じます。自然素材の包みには、作り手の丁寧な気持ちが伝わる力があるのかもしれませんね。
そして忘れてはならないのが、「おひつ」の存在です。炊きたてのご飯をそのまま鍋に置いておくと、水分がこもってしまい、冷めるとベチャッとしがちです。ところが、おひつに移すと木が余分な水分を吸い取り、ほどよいしっとり感を残してくれます。その結果、冷めてもお米がふっくら。おむすびにしたときの口当たりが格段に違います。まさに「ご飯を美味しくする魔法の道具」なのです。
おひつに使われる杉や檜(ひのき)は、香りもよく、抗菌性にも優れています。昔の人々は、理にかなった素材を自然の中から選び、暮らしに取り入れてきました。忙しい現代では電気ジャーが当たり前ですが、あえておひつを使ってみると、ご飯の美味しさを改めて実感できるはずです。
また、おむすびを握るときの「手」も、立派な道具のひとつ。手のひらの温度でご飯の表面がほんのり締まり、絶妙な食感を生み出します。強く握りすぎず、ふんわり包み込むように──。そのリズムや力加減は、まるで音楽のように人それぞれ違います。まさに「自分だけの味」を作り出す瞬間です。
最近では、木型やシリコン製の型を使って形を整える人も増えています。忙しい朝でも手軽にきれいなおむすびが作れる便利なアイテムですね。けれども、手で握るときの温もりには、どんな道具にも代えがたい魅力があります。人のぬくもりが加わることで、おむすびは単なる食べ物ではなく、“想いを結ぶ”存在になるのです。
おむすび作りには、たくさんの道具と知恵が息づいています。昔ながらの良さと、現代の便利さ。その両方をうまく取り入れながら、あなたもぜひ“自分らしいおむすび道具”を見つけてみてください。どんな素材を選び、どんな手で握るか──そのひとつひとつが、きっと世界にひとつだけの味になるはずです🍙