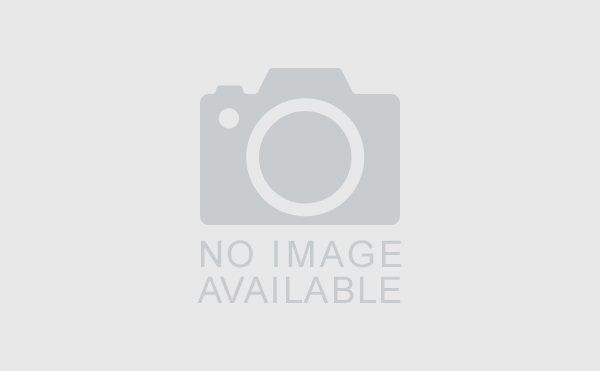おむすびと相性抜群!「海苔」の意外なヒミツ
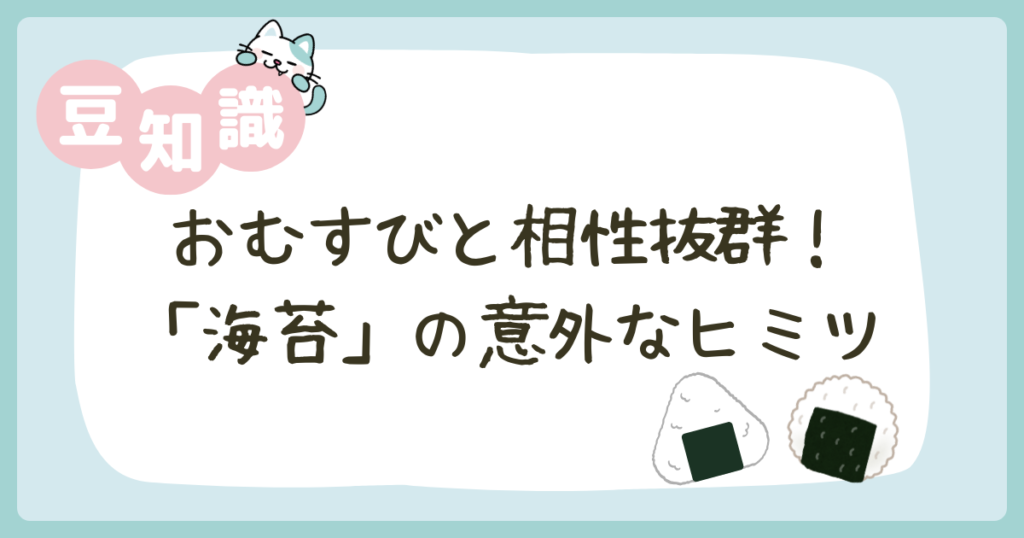
こんにちは、にゃおむすびです!
おむすびの顔ともいえる“海苔”。コンビニおにぎりでも、手づくりのおむすびでも、あの黒々とした海苔が巻かれていると、なんだか安心感すらありますよね。でも、実は「おむすびに海苔を巻くようになった」のは、意外と最近のことだと知っていますか?
海苔の歴史は古く、奈良時代の文献にも登場しますが、当時は“板海苔”のような形ではなく、佃煮のように加工されていたり、自然に採れる“岩海苔”のようなものが中心でした。現在のような「紙のように薄く伸ばして乾燥させた板海苔」が登場したのは江戸時代に入ってからのこと。海苔づくりの技術が発展し、江戸前寿司や、おむすびに巻く文化が徐々に広がっていったのです。
では、なぜおむすびに海苔を巻くようになったのでしょうか?
ひとつは「手を汚さずに食べられるようにするため」。外で食べる機会が多かった江戸の人々にとって、手で持ちやすいというのはとても大事なポイントでした。もうひとつは「お米の乾燥を防ぐため」。おむすびは時間が経つと表面がパサつきやすくなりますが、海苔で包むことで適度に保湿され、食感が守られるのです。
そしてもうひとつ、見逃せないのが“風味の相乗効果”。炊きたてごはんの甘みと、海苔の香ばしさは絶妙なハーモニー。味覚的にも、おむすびと海苔は最強コンビといえるでしょう。
ただし、最近では「巻かない派」のおむすびも増えています。特に具材の風味を前面に出したいときや、見た目に変化をつけたいときには、海苔をあえて使わないことも。にゃおむすびでも、海苔なしで素材の味を楽しむメニューがあるのは、まさにそうした発想からなんです。
ちなみに、海苔にはビタミンやミネラルが豊富に含まれ、鉄分や食物繊維もたっぷり。栄養面でも優秀な食材なんですよ。
次におむすびを食べるときは、海苔の「味・香り・食べやすさ」に、ちょっと意識を向けてみてください。きっと、いつもよりちょっとだけ美味しく感じられるかもしれません。